再生可能エネルギーの創製は、世界共通の使命。
――寺澤先生の研究内容について教えてください。
主に太陽電池材料の創製に取り組んでいます。現在、地球温暖化やエネルギー資源の枯渇を防ぐため、2050年までにカーボンニュートラルを達成することが国際的な目標となっています。しかし日本は全発電電力量の多くを天然ガスや石炭など化石燃料に頼っているのが現状です。そのため超スマート社会構築に向けて、主力電力を再生可能エネルギーへシフトチェンジしていくことが世界的にも求められています。その再生可能エネルギーの代表格として注目をされているのが太陽光発電です。その太陽光発電も、2050年までに現在の約20倍の発電容量が必要とされているのですが、従来の技術延長ではその実現は困難であり、新技術によるパラダイムシフトが求められています。
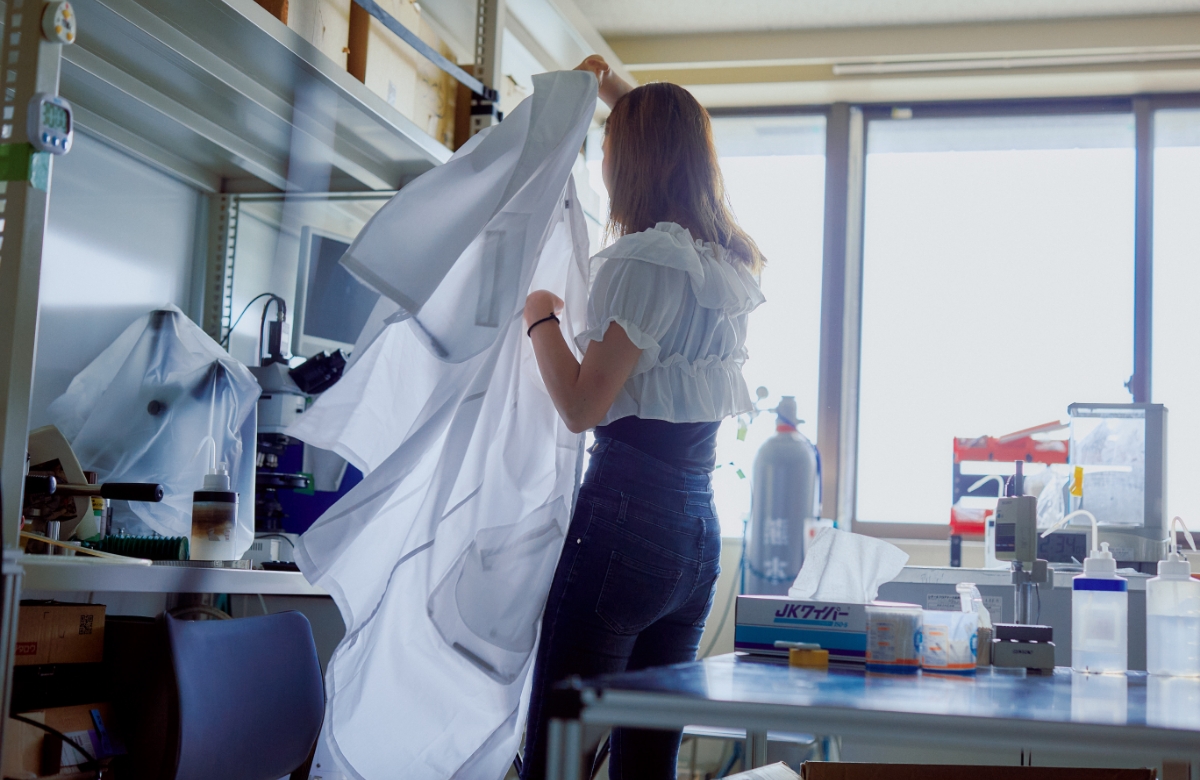

これまでにない太陽電池材料を!
――新技術による太陽電池材料の開発について。具体的にどのようなご研究をされているのでしょうか。
私が所属する研究室では、次世代の太陽電池材料として『強誘電体』に注目して研究を進めています。強誘電体の特長は、従来の半導体太陽電池材料を凌駕する高電圧を発生させる能力があることです。一方で、高電圧の発生を実現するためには結晶構造の対称性の破れが必要です。しかしながら、強誘電体太陽電池材料に使われる無機結晶においては対称性の破れの制御が非常に困難であり大きな課題となっています。そこで、有機分子の非対称性を利用し、有機分子を無機結晶に融合させることで無機結晶の対称性を大きく破らせた強誘電体を創製しています。
現在はまだ基礎研究の段階でラボスケールでの小規模な実験なので、屋根や斜面に設置される太陽電池のような実用化までには時間を要しますが、従来の太陽電池材料を超える性能を持つ材料は、エネルギー変革を支える一助となると考えています。
生命医科学から工学へと転換、そのきっかけ
――寺澤先生は生命医科学のご出身。研究分野を工学へと転換されたきっかけは?
もともと生命医科学の出身で、生理学や生化学、分子細胞生物学や遺伝学などを学んでいました。当時所属していた生命医科学科は、多様なバックグランドの先生たちを集めてつくられた異分野融合のカラーが強い学科でした。そのような環境にいたこともあり、研究室では私は物質の左右性に関する研究をしていましたが、普段から自身の専門や研究分野以外のものに触れる機会も多かったです。その中でたまたま強誘電体という分野に出会い、次第に材料を自在につくることができる工学分野にも興味を持つようになりました。その結果、材料開発要素の強い現在の研究室で研究をすることに決めました。
また、研究分野を転換することにはまったく迷いはありませんでした。自分の興味のあることを追求できることの方が嬉しかったからです。私自身は生命系の学科でありながら、物質の左右性の研究をしてく中で物理や化学の研究者とも共同で研究を行うことで、視野を広げることができました。他分野の研究者とディスカッションすることで、自分の研究の盲点に気づいたり、新しい発見に繋がることが多々ありました。そのような経験から「分野にとらわれることなく、視野を広げるべき」という考えが私の根底にあります。


初めての九州、初めての熊本
――熊本に赴任されてどんな毎日を送られていますか。
現在は大学で教鞭を執りながら、学生たちと共に研究を進めています。私の所属する研究室には情報出身の学生が多く、実験経験がない学生も多いです。そうした学生たちには、基礎から実験のやり方を教え、自分で手を動かして理解することの大切さを伝えています。教える際には、できる限り学生一人ひとりの理解度に合わせた指導を心がけています。座学だけではなく、実際に実験を通じて理論と実践を結びつけることが重要だと思っているので、自分でいろいろ考える癖をつけてほしいなと思います。
熊本はまったく地縁がなかったので、こちらに来てすぐは土地勘や情報が皆無で、方言がわからないこともあったりして、思わぬところで苦労したこともありました。熊大のシステムも全然わからず、一つのことをやるのにかなり時間がかかりました。その一方で、阿蘇に遊びに行ったとき、阿蘇山の壮大さには感動しました。同じ日本にこんな素晴らしい景観があるなんて…という新鮮な驚きとともに、自分はこれまでなんて狭い範囲で生きていたんだろうとも思ってしまいました。それほど雄大な阿蘇には惹きつけられました。また、熊本に住み始めてからは九州一円や西日本への旅行に行くことが多くなりました。食べ物は何でも新鮮でおいしいなと感じます。まだまだ巡れていない土地がたくさんあるので、熊本を拠点に西日本再発見の旅は続けてみたいです。
やりたいことは迷わずトライし、自分以外の視点に気づこう。
――最後に、学生さんたちにメッセージをお願いいたします。
学生たちに伝えたいことは、「自分がやりたいと思ったことは、勉強でも遊びでもなんでもやってみる」ということです。実行することが経験値になるのはもちろんですが、「あとでやろう、いつかしよう」と思っていても、その「いつか」はもしかしたら永遠にこないかもしれません。それが人でも、場所でも、イベントでも、「あの時にやっておけばよかった」という後悔は、何かの機会を失ったことになります。やりたいことにはできるだけトライし、自分が知らない世界や文化、考えにたくさん触れると良いと思います。そのような多様な経験を通して、自分がどのような生活を送りたいか見えてくると思います。


